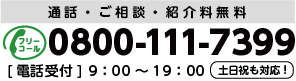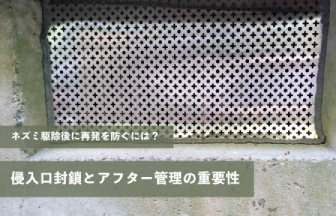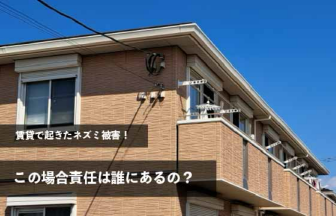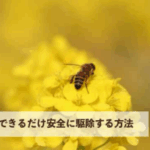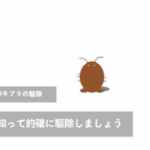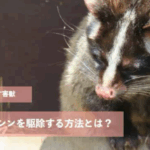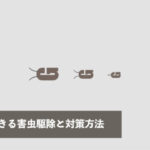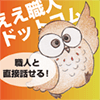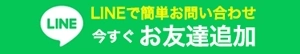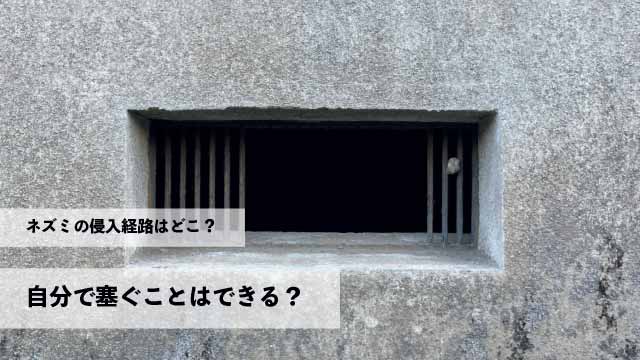
ネズミは小さな体を活かして、わずか1〜2cmの隙間があれば簡単に建物内に侵入してしまうってご存知でしたか?。
気がつけば天井裏や壁の中、床下などに巣を作り、糞尿や騒音、断熱材の破壊といった被害を引き起こします。
「ネズミを見かけた」「物音がする」といった兆候がある場合、その背景には必ず“侵入経路”の存在があります。
いくら駆除をしても、侵入口を放置していれば被害は再発してしまうのです。
この記事では、ネズミの代表的な侵入経路やその塞ぎ方、自分で対応できる範囲と注意点、そして最も安全かつ確実な対策として専門業者に依頼すべき理由について解説します。
ネズミが侵入する代表的な場所

ネズミの侵入経路は、建物の劣化や構造的な弱点を突いていることが多く、一見気づきにくい箇所も少なくありません。
以下に主な侵入ポイントを紹介します。
通風口・換気口
屋根裏や壁の中に空気を循環させるために設けられている通風口。
古くなってガラリが破損していたり、網がついていない場合、ネズミにとっては絶好の侵入経路になります。
特に屋根裏につながる換気口は、室内とほぼ直結しているため、知らぬ間にネズミの巣になってしまうこともあります。
排水管・下水管
ドブネズミのように泳ぎが得意な種類は、排水管や下水管を通って建物内に侵入してくることがあります。
古い建物でトラップ(臭気止め)が破損していると、ネズミが簡単に這い上がってくる可能性があります。
また、雨水管やベランダの排水口にも注意が必要です。
網目のカバーを設置していない場合は格好の侵入路になります。
扉・サッシ・窓の隙間
玄関や勝手口を一時的に開けている間に、素早く侵入されるケースも少なくありません。
ネズミは夜行性で、人の目を盗んで行動する習性があるため、ほんの数十秒の油断が命取りになることも。
また、老朽化したサッシや窓枠の隙間も要注意です。
1cm程度の隙間でも頭が通れば侵入できるため、しっかりと確認しましょう。
換気扇・給排気口
特にキッチンやトイレ、風呂場などにある換気扇や給排気口。
使用していない時間帯には静止しているため、外部と建物内部を繋ぐ“抜け道”になってしまいます。
防虫ネットやメッシュが付いていない場合や、ファン部分が破損している場合はネズミが侵入しやすい構造になっています。
自分で侵入経路を塞ぐ方法と注意点

ネズミの侵入経路を突き止めた場合、即座に塞ぐ対策が必要です。
まずは以下のような方法を実践してみましょう。
応急処置の基本
・破損したガラリは新品に交換する
・開けっ放しの扉は厳禁、注意喚起を徹底する
・排水口にはストッパーやメッシュキャップを設置する
・小さな隙間は金属製パテや防鼠材で塞ぐ
・使用していない換気扇には金網やフタを取り付ける
簡易的な方法として、侵入口と思われる穴や隙間にガムテープを貼ってみるのも効果的です。
数日後に破れていたり、内側から食い破られていた場合は、そこが侵入経路だった可能性が高いです。
素人施工での限界
ただし、ネズミは木材やプラスチックなどの柔らかい素材であれば簡単にかじって突破します。
仮に一度塞げたとしても、再侵入されることは珍しくありません。
また、建物全体をくまなくチェックして、すべての侵入口を特定・処置するのは非常に手間がかかり、専門的な知識と経験がなければ難しいのが現実です。
ネズミの侵入防止には専門業者への依頼が最も確実
ネズミは極めて賢く、警戒心が強く、適応能力に優れた動物です。
1匹駆除したとしても、複数の個体が潜んでいたり、すでに繁殖していることもあります。
さらに、侵入経路の完全な封鎖をしなければ、たとえ一度は追い出せても、またすぐに戻ってくる可能性があります。
市販の罠や毒餌、簡易パテなどでは限界があり、「やってみたけど再発した」という相談が非常に多いのが現状です。
こうした背景から、ネズミの侵入経路を正確に特定し、専門的な資材と技術でしっかりと封鎖するには、やはりプロの力を借りるのが最も確実かつ安全な方法です。
まとめ

ネズミは、わずかな隙間でも簡単に侵入してくる厄介な害獣です。
通風口、排水管、換気扇など、意外なところが侵入経路になっている場合も多く、素人の目ではすべてを把握するのは困難です。
応急処置として自分でできる対策もありますが、再発リスクや安全性の観点から見ても、最終的には専門業者に依頼するのが確実です。
ネズミの被害は時間が経つほど深刻化しやすいため、早めの対策が重要です。
「一網打尽」は、全国の害虫・害獣駆除業者を掲載しているポータルサイトです。
ネズミの駆除や再発防止に関して経験豊富な業者が多数登録しており、お住まいの地域に応じた最適な対応を受けることができます。
「自分でやってみたけどダメだった」「再発して困っている」という方は、ぜひ一網打尽を活用して、信頼できるプロに相談してみてください。