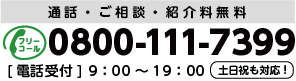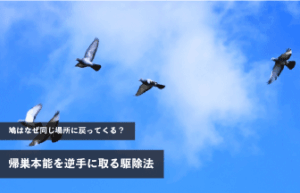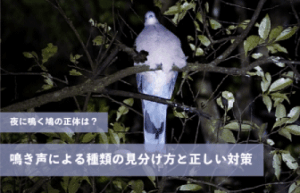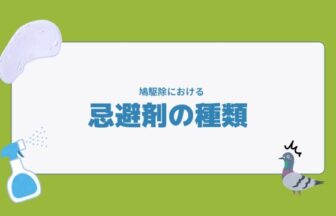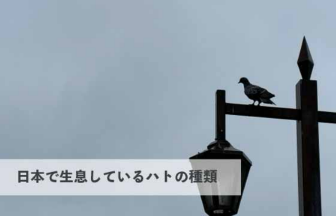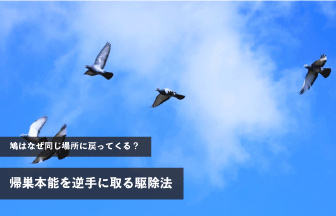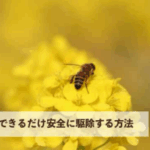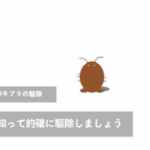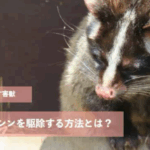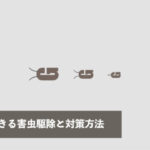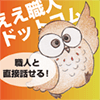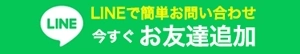「毎朝ベランダが鳩のフンだらけでストレス…」
「専門業者に頼む前に、なんとか自分で対策したい!」
そんな悩みを抱える方に注目されているのが、ハイターやカビキラーなど身近な生活グッズを使った鳩対策です。
普段キッチン用品の漂白や、お風呂場のパッキンのカビ取りなどで大活躍のハイターやカビキラー。
本当に鳩よけなんかに効果があるの?と思われるかもしれませんが、
実はこれらの塩素系漂白剤には、鳩が嫌うニオイや刺激があり、「鳩よけ」として一定の効果があるとされています。
この記事では、ハイターやカビキラーを使った鳩対策の具体的な方法、注意点、他にも使える身近なグッズ、そして本格的な駆除が必要なケースについてまで、徹底的に解説していきます。
「まずはできることから始めたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
鳩被害の実態とリスクとは?
公園や街中でよく見かける鳩は、一見おだやかで人懐っこく見える存在です。しかし、そんな鳩が住宅のベランダや屋根などに住み着いてしまった場合、その影響は見た目以上に深刻です。
一度「ここは安全な場所」と判断されてしまうと、鳩は何度追い払っても戻ってくるようになり、日々の暮らしや健康、住宅の資産価値にまで大きな悪影響を及ぼすようになります。
以下では、鳩によってもたらされる主な被害とリスクについて、具体的に解説します。
鳩フンによる被害
鳩被害の中でもっとも多く報告されているのが、フンによる衛生被害や環境悪化です。
衛生面の悪化
鳩のフンには見た目だけでなく、重大な病原菌やカビが含まれていることが知られています。
たとえば以下のような病原体が検出されています。
- クリプトコッカス:肺や脳に感染し、髄膜炎を引き起こすこともある真菌(カビ)
- ヒストプラズマ:鳥のフンに含まれるカビの一種で、吸い込むことで肺に感染する
- オウム病(クラミジア・サイトアキ):鳩などの鳥類が保菌し、吸引や接触で人に感染する可能性がある
特に免疫力が低い乳幼児や高齢者、基礎疾患を持っている方がいる家庭では、呼吸器感染やアレルギー反応のリスクが高まるため、注意が必要です。
害虫の発生
フンを放置することで、周辺にダニ・ノミ・ハエ・ゴキブリなどの害虫が繁殖する可能性もあります。鳩の羽毛に寄生するダニが人間に移る「鳥ダニ症」では、皮膚のかゆみや湿疹、炎症などの症状が報告されています。
害虫の発生は室内にも影響を与えやすく、ベランダに干した洗濯物への付着や、室内への侵入といった二次被害を招く恐れもあります。
悪臭の発生
鳩のフンは乾燥するまでは特有のアンモニア臭を放ちますが、これが夏場の高温多湿な時期にはより強烈な悪臭となり、洗濯物へのニオイ移りや窓を開けづらいといった不快感につながります。
マンションなどでは、共有スペースにまで臭いが広がり、近隣住民とのトラブルの原因になることも。
建物の劣化
鳩フンに含まれる尿酸は非常に強い酸性で、金属部分の腐食やコンクリートの劣化を進行させることが確認されています。
特にベランダの手すり、外壁、エアコン室外機の上などにフンが蓄積すると、住宅の見た目が悪くなるだけでなく、資産価値の低下や修繕コストの増加にもつながります。
鳴き声・羽音によるストレス
鳩は昼行性で、特に早朝や夕方に活発に活動します。
この時間帯に、「グルルル…」「ポーポー」という鳴き声や、バタバタという羽ばたき音が繰り返されることで、睡眠の妨げや精神的なストレスになるケースが増えています。
近年では「環境騒音」として扱われることもあり、マンションや団地では近隣からの苦情や管理組合への相談が多発する原因の一つになっています。
特に注意すべき家庭環境
鳩による被害はすべての家庭にとって厄介なものですが、特に以下のような世帯では、より一層の注意が求められます。
小さなお子様がいる家庭
小児は大人よりも免疫機能が未発達であるため、鳩フンに含まれる病原体の影響を受けやすくなります。ベランダに出て遊ぶ機会も多いため、フンに触れたり吸い込んだりするリスクが高まります。
高齢者や持病のある方がいる家庭
高齢者や持病(特に呼吸器疾患)を持つ方は、わずかなカビや細菌でも健康被害を受けやすい傾向があります。肺炎などを引き起こす病原体が鳩のフンに含まれているため、早急な対応が必要です。
ペットを飼っている家庭
犬や猫などのペットがベランダに出た際に鳩フンを踏んだり、なめてしまったりすることで、感染症や体調不良のリスクがあります。ペットは人間よりも小さな刺激に敏感であるため、些細な衛生環境の悪化でも体調に影響が出ることがあります。
ハイターやカビキラーは鳩対策に効果があるのか?

「ベランダにいつの間にか鳩が住み着いているけど、専用の鳩よけグッズを買うのは面倒…」「何か家にあるもので対策できないかな?」
そんな方の間で近年注目されているのが、ハイターやカビキラーなどの塩素系漂白剤を使った“鳩よけ”です。これらの家庭用洗剤は、本来はカビや汚れを落とすためのものですが、その成分が鳩の嫌がる性質を持っていることから、簡易的な忌避手段(=近づけさせない)として活用されることがあります。
では、なぜこのような洗剤が鳩にとって不快なのでしょうか?その理由を詳しく見ていきましょう。
なぜ効くのか?成分の特性
1. 塩素系漂白剤特有のツンとしたニオイ
ハイターやカビキラーに含まれる次亜塩素酸ナトリウムなどの成分は、強烈な刺激臭(いわゆる“プールのようなニオイ”)を放ちます。人間にとっても刺激があるこのニオイは、動物にとってはより異質で不快なもの。
鳩は人間ほど嗅覚が鋭くはないとされていますが、「慣れないニオイ」には強い警戒心を抱くという習性があります。
このため、普段と違う環境を感じた鳩は、「ここは危険かもしれない」と感じて近づかなくなる可能性があります。
2. 強い刺激性のガス(塩素ガス)
高温多湿な場所や直射日光の下で塩素系漂白剤が揮発すると、微量ながら塩素ガスが発生することがあります。これも鳩にとっては居心地が悪くなる要因のひとつです。
特にベランダの手すりやエアコン室外機の上など、鳩が“とまり木”として選びやすい場所にこのニオイや刺激があると、長時間滞在しにくくなると考えられます。
3. 鳩は「変化」に敏感
鳩は非常に順応性の高い生き物ですが、それと同時に環境の変化には敏感です。これまで安全だった場所に急に刺激臭が漂ったり、視界や音に変化があったりすると、「ここには戻らない方がいい」と判断する傾向があります。
そのため、漂白剤のニオイという「いつもと違う要素」を取り入れることは、あくまで一時的な鳩よけとして効果が期待できるというわけです。
「追い払う目的」限定という注意点
ここで強調しておきたいのは、ハイターやカビキラーの使用は“忌避(きひ)目的”に限られるという点です。
つまり、
- 鳩が止まりにくくなるような環境をつくる
- すでに住み着いている鳩を間接的に遠ざける
といった使い方は問題ありませんが、
- 鳩に直接吹きかける
- 鳩の巣やヒナに向けて使用する
- 鳩が触れて明らかに有害となる場所に薬剤をまく
といった行為は、動物への攻撃や駆除行為と見なされる可能性があります。
鳥獣保護法との関係
日本国内では、鳩を含む多くの野鳥が「鳥獣保護管理法」によって保護されています。この法律では、許可なく野鳥を傷つけたり、捕まえたり、殺したりする行為を禁じており、違反すると以下のような処罰を受ける可能性があります。
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(個人の場合)
- 鳩の巣・卵の無断撤去も原則禁止
したがって、漂白剤を使った鳩対策を行う際は、鳩そのものに害を加えないよう細心の注意を払う必要があります。
あくまで「居心地が悪くなる環境づくり」を目的に、適切な範囲での使用を心がけましょう。
忘れてはいけない「安全対策」
ハイターやカビキラーを使う場合、人間側の健康や住宅設備への影響にも注意しなければなりません。
- 換気が悪い場所での使用は避ける:屋外であっても、風通しの悪い場所では成分がこもりやすく危険です。
- 子どもやペットの手が届かない場所で使用する:薬剤が残っている場所を舐めたり触ったりすると、健康に悪影響が出る恐れがあります。
- 金属や布製品への付着に注意:漂白成分が付着すると、腐食や変色の原因になります。
また、使用後は水拭きや乾燥などの後処理をしっかり行うことも大切です。
ハイターやカビキラーを使った鳩対策の方法

ここでは実際に、ハイターやカビキラーを使って鳩を「寄せ付けない」ための方法を解説します。
ステップ1:フンの除去・清掃
まずはベランダや手すり、エアコン室外機などに付着した鳩フンをきれいに掃除しましょう。フンのニオイが残っていると、鳩が再び戻ってきやすくなります。この作業ではゴム手袋・マスクを着用し、フンを取り除きます。水で流す前に紙や布で拭き取るのがポイントです。そして最後にカビキラーなどを噴霧して消毒を行います。
ステップ2:ハイターを使って忌避エリアを作る
水で2〜3倍に薄めたハイターをスプレーボトルに入れ、鳩が止まりやすい手すり・ベランダの縁・エアコン室外機の上などに散布します。一度乾いたら、2〜3日に1回程度の頻度で再度噴霧するとより効果的です。
ステップ3:安全面への配慮
使用後はしっかりと換気を行うことが大切です。また、小さなお子様やペットが舐めないように、乾燥してから立ち入り可にするようにしましょう。漂白作用があるため、衣類や植木などにかからないよう注意することも忘れないでください。
絶対NGな使用方法
- 鳩に直接かける
- 鳩の巣にかける
- 高濃度で散布して放置する
これらは法的に問題があるだけでなく、近隣とのトラブルや火災の原因にもなりかねません。
ハイターやカビキラー以外の「身近な鳩対策グッズ」
家庭内にあるものでできる鳩対策は、他にもいくつかあります。
視覚を刺激するアイテム
- アルミホイルやCDを吊るす→ 光の反射が鳩の警戒心を刺激する
- カラスやヘビの置物→ 天敵の存在を模して鳩を遠ざける
音や動きで威嚇するアイテム
- ペットボトル風車やモビール→ 風や動きによる変化を嫌う習性を活用
- 風鈴や鈴→ 突然の音に驚いて寄りつかなくなる
自作忌避剤
- 唐辛子水スプレー→ 鳩の足裏に刺激を与え、長居しづらくする
- お酢やレモン汁→ 酸性のニオイを嫌う習性を利用
防鳥ネットやワイヤー
- ベランダや手すりに物理的なバリアを作ることで、鳩の「止まり場」をなくす
これらのグッズは100円ショップやホームセンターでも手に入りやすく、手軽で経済的な対策として人気があります。
注意!やってはいけない鳩対策

鳩対策には、効果が期待できる方法だけでなく、法律違反やトラブルの原因になるNG行為も存在します。
鳥獣保護法に注意
日本では鳩も「鳥獣保護管理法」によって保護されており、以下の行為は原則として違法です。
- 鳩を傷つける・捕獲する
- 巣や卵を勝手に撤去する(※自治体の許可が必要)
違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
近隣トラブルのリスク
- 自宅から追い払った鳩が隣家に移動してしまう
- 忌避剤のニオイが隣人宅にまで漂ってクレームに発展
- ベランダへの設置物が景観を損ねるとトラブルに
鳩対策は自宅だけの問題ではないため、近隣住民との調和も意識することが大切です。
自力対策で効果がないときは業者へ相談を
ハイターや生活グッズによる鳩対策は、手軽に始められる反面、一時的な効果に留まるケースも多いです。
鳩の「帰巣本能」が壁になる
鳩は一度「ここが安全で快適」と覚えた場所には、何度追い払っても戻ってくる傾向があります。特に巣を作っていた場合、その執着は非常に強く、毎日のように同じ場所に戻ってきてしまうこともあります。
専門業者の対応内容
- フンや巣の徹底清掃・消毒
- 物理的な防鳥施工(ネット・剣山など)
- 忌避剤の専門的散布
- 再発防止のアドバイス・定期点検
プロの業者であれば、安全かつ合法的に、根本的な解決策を提供してくれます。
「一網打人」では、全国の実績ある鳩駆除業者を無料でご紹介しています。強引な営業や見積もりの押しつけは一切ありません。自分でできる対策で効果が出ないと感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
鳩はフンや鳴き声による被害だけでなく、健康リスクや住宅劣化にもつながる厄介な存在です。
ハイターやカビキラーは、その臭いや刺激によって鳩が「住みにくい」と感じる環境を作るのに有効ですが、使用にあたっては、安全面と法律の順守が不可欠で、誤った使い方は法的トラブルにもつながります。
身近な対策で効果がないときは、専門業者による「物理+衛生+再発防止」の一貫対応が有効です。
「一網打人」では、安心して依頼できる優良業者を無料でご紹介しています。
「ちょっと気になる…」と思ったその時が、対策のタイミングです。 まずはできることから、鳩被害のない快適な住まいを取り戻しましょう。