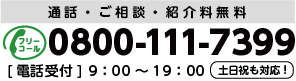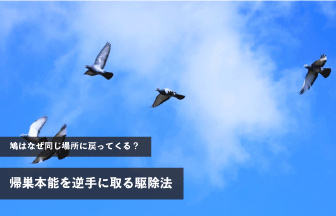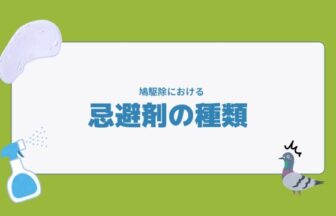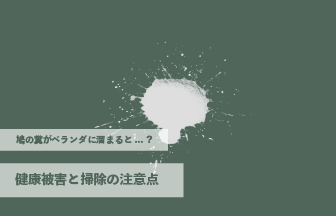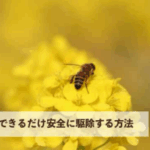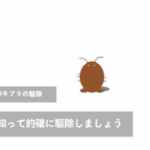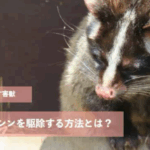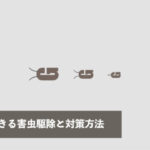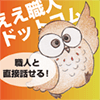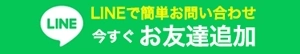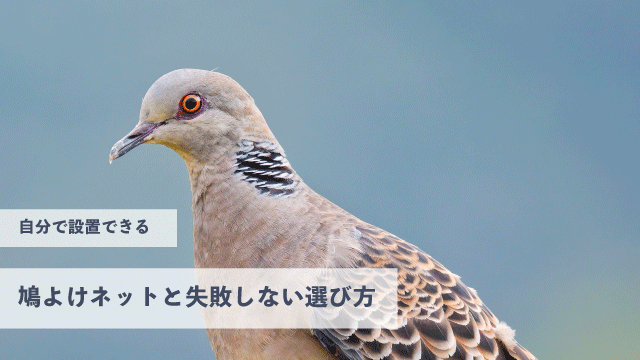
「ベランダに鳩が住みついてしまった」「フンが毎日落ちていて掃除が大変…」
そんな悩みを抱えている方にとって、鳩よけネットは有効な対策の一つです。
この記事では、自分で設置できる鳩よけネットの選び方と正しい設置方法、注意点まで徹底解説。
鳩被害に悩まされないためのポイントをわかりやすくご紹介します。
目次
なぜ鳩よけネットが効果的なのか?

鳩による被害に悩む家庭や施設は年々増えています。
フン害や騒音、ダニや病原菌の媒介といった健康リスクに直結するため、早めの対策が重要です。
その中でも「鳩よけネット」は、最も確実性が高く、再発防止にもつながる物理的な防除策として、多くの現場で採用されています。
では、なぜ鳩よけネットがこれほど効果を発揮するのでしょうか。
ここでは、その仕組みと特徴を詳しく解説します。
鳩は「入りにくい」「居心地が悪い」場所を避ける
鳩は都市部でも頻繁に見かける身近な鳥ですが、実は非常に繊細で警戒心が強い生き物です。
人の気配や音、周囲の変化に敏感で、わずかな違和感でもその場所を避ける傾向があります。
とくに、「入りにくさ」や「不安定さ」を感じる場所には巣を作りたがらない習性があります。
鳩は安全で落ち着いた場所を好むため、ベランダやバルコニーに視界を遮るネットが張られているだけで、「ここは安心できない」「落ち着いて過ごせない」と判断し、その場所に近づかなくなります。
また、鳩は一度巣作りを始めた場所に執着し、何度も戻ってくる「帰巣本能」が強い鳥でもあります。
ネットを使ってその行動パターンを物理的に遮ることは、再侵入を防ぐうえでも非常に有効です。
つまり、鳩よけネットは「ここには住めない」と鳩に認識させ、根本的な侵入動機を断つ効果があるのです。
ネットは「物理的ブロック」の代表格
鳩対策にはさまざまな方法がありますが、その中でも鳩よけネットは数少ない「侵入そのものを防ぐ」手段です。
いわゆる「物理的ブロック」に分類される方法で、鳩にとっては見た目以上に大きな障壁となります。
たとえば、市販されている忌避剤(臭い・味・粘着性のある物質)や、超音波装置、スパイクなども対策として知られていますが、これらには以下のような弱点があります。
- 忌避剤:時間が経つと効果が薄れ、雨風で流されやすい
- 超音波装置:周囲の環境や電源状態に左右され、鳩が慣れることもある
- スパイク:鳩がその周辺のスペースを避けて、別の場所に止まることがある
これに対して、ネットは鳩の行動範囲そのものを封鎖できるため、鳩がベランダや窓際に近づくこと自体を物理的に不可能にします。
設置後すぐに効果が現れ、鳩が一度その場を避ければ、再び戻ってくる可能性も低くなります。
さらに、ネットは維持管理が比較的簡単で、効果が長持ちする点も大きなメリットです。
耐候性・防炎性のある素材を選べば、数年単位での使用も可能。
適切に固定されていれば、台風や強風にも耐えうる強度を発揮します。
「見た目よりも効果重視」が鳩対策の基本
「ネットを張ると景観が悪くなるのでは…」とためらう方も多いですが、最近では目立ちにくい色味(グレー・ブラックなど)や細かい網目のデザイン性を考慮した商品も多く登場しています。
景観と実用性を両立させるネットを選べば、違和感の少ない仕上がりになります。
鳩被害は放置すればするほど深刻化し、掃除や衛生管理、健康被害のリスクが膨らんでいきます。
「見た目が気になる」よりも「快適で衛生的な生活空間を守る」ことを優先すべきというのが、実際に被害を経験した方の共通した声です。
鳩よけネットは「予防」にも「再発防止」にも効果的
鳩よけネットは、すでに被害が出ている場所だけでなく、これから被害が出そうな場所の「予防策」としても非常に有効です。
特にマンションの高層階やビルの屋上など、風通しがよく静かな空間は、鳩にとって好都合な営巣場所になりやすいため、事前にネットを設置しておくことで被害の発生そのものを防げます。
また、過去に鳩が巣を作っていた場所は、「鳩の記憶」に残っているため、ネットを張らない限り再び戻ってくる可能性があります。
繰り返し鳩に悩まされているなら、ネットによるブロックがもっとも確実な解決策です。
自分で設置できる鳩よけネットの種類
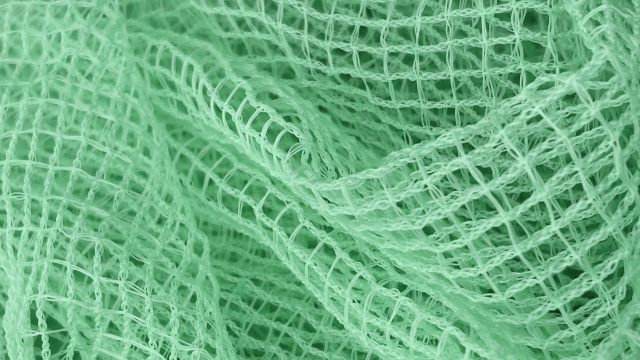
市販されている鳩よけネットにはさまざまな種類があり、設置場所や目的に合わせて選ぶことが重要です。
ポリエチレン製ネット(標準タイプ)
- 軽量で扱いやすく、DIY向けとして定番
- 紫外線に強く、屋外でも劣化しにくい
- 網目サイズ:1.5〜2cm前後が一般的
【おすすめの使用場所】
ベランダ・バルコニー・エアコン室外機周辺
ステンレス製ネット(ハードタイプ)
- 強度が高く、長期間設置したい場合におすすめ
- 鳩のくちばしでも破れにくい
- やや重く、しっかりした固定が必要
【おすすめの使用場所】
工場、倉庫、高所などのプロ向け現場
防炎ネット
- 火災対策が必要な建物や高層住宅に最適
- 防炎性能付きの素材で安心して使える
- 価格はやや高め
【おすすめの使用場所】
集合住宅・商業ビル・公共施設の高層階
鳩よけネットを選ぶときのポイント
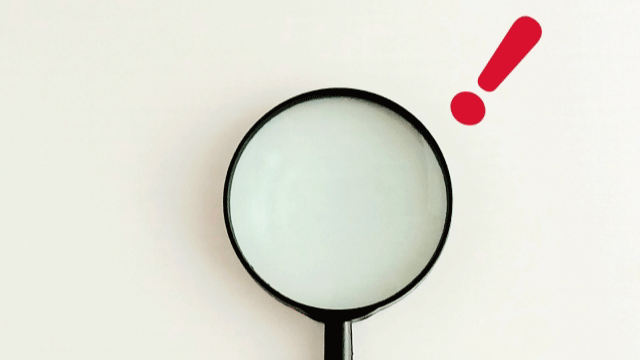
網目のサイズに注意
鳩は意外と体を小さくして狭い場所に入り込めます。
網目が3cm以上だとすり抜けられることがあるため、1.5〜2cm程度のものが安全です。
カラー選びも効果に影響
- グレーや黒:目立ちにくく、景観に配慮できる
- 白や青:視認性が高く、鳩に対する威嚇効果が期待できる
※設置場所に合わせて選びましょう。
耐候性・耐久性もチェック
太陽光や雨風にさらされるため、屋外用の耐候性素材を選ぶことが長持ちのカギになります。
特に南向きや風の強い地域では、UVカット加工や補強付きのネットが安心です。
鳩よけネットの設置方法と手順
用意する道具
- 鳩よけネット(選んだサイズ・素材のもの)
- 結束バンドまたはワイヤー
- ハサミ・カッター
- 脚立や踏み台(高所作業用)
設置ステップ

1. 取り付け場所の確認と清掃
まずはベランダの周囲を清掃し、フンや巣がないか確認します。
衛生面を考え、清掃時はマスク・手袋着用を忘れずに。
2. ネットを仮あてしてサイズを確認
ベランダの開口部に合わせて、ネットの長さ・幅を仮あてします。ぴったりすぎるとたわみが出るため、やや余裕をもってカットするのがコツ。
3. 固定具でしっかり留める
手すりや壁面に沿って、結束バンドやフック、金具などでネットを固定します。
隙間があると鳩が侵入するため、すき間は絶対に残さないことが重要です。
4. 定期的に点検・補修を
風や紫外線で劣化することがあるため、数ヶ月に一度は点検してほつれや破損があればすぐに補修しましょう。
自分で設置する際の注意点
高所作業のリスク
ベランダの外側に乗り出しての作業や、2階以上での取り付けは転落の危険があります。
不安な場合は無理をせず、専門業者への相談も検討しましょう。
電線や配管に触れないよう注意
ネットを張る位置によっては、エアコンの配管や電気配線に接触する可能性があります。
感電や火災のリスクがあるため、必ず安全を確認しながら作業しましょう。
それでも鳩被害が止まらないときは?

ネットを設置しても、すでに鳩のフンが多量に付着していたり、ダニが繁殖していたりする場合は、ネットだけでは根本解決にならないことがあります。
こうしたケースでは、以下の対応が必要です
- フンの専門的な清掃・消毒
- 鳩の「営巣」状況の確認と、法に基づく適切な撤去
- ネットと併用した忌避剤や威嚇グッズの導入
- 再発防止のための現地調査と防除計画
自分でできる鳩対策に限界を感じたら?
自力での対処が難しいと感じたら、無理せずに鳩対策の専門家に相談するのがおすすめです。
専門家に依頼することで、法律に沿った適切な対応ができるほか、高所での作業や鳩の巣の撤去も安全に行えます。
また、お客様の状況に合わせて、ネットだけでなく複数の対策を組み合わせた効果的な解決策をご提案することも可能です。
まとめ
鳩よけネットは、適切に選び、正しく設置すれば高い効果を発揮するアイテムです。
ただし、設置の仕方を誤ると、鳩が隙間から侵入してしまったり、逆に見た目が悪くなってしまうこともあります。
「鳩が来る前に」対策するのが最もコスパが高く、生活への影響も最小限で済みます。
DIYが難しいと感じたら、無理をせず、実績あるプロに依頼するという選択肢も検討しましょう。
「一網打人」では、全国の害鳥・害獣駆除に対応した優良業者をご紹介しています。
無料相談・現地調査・お見積りが可能な業者も多数掲載。ベランダや屋根、太陽光パネルの被害など、どんな鳩被害でも安心してご相談ください。