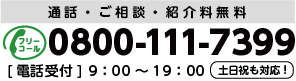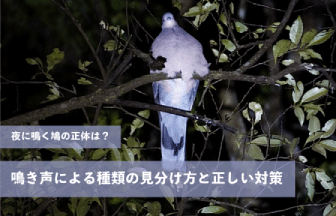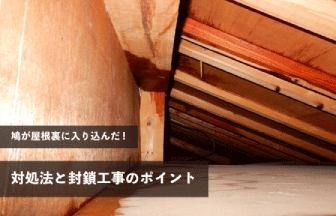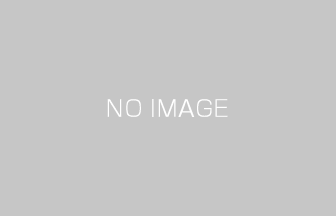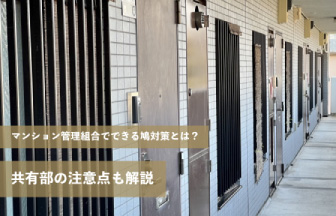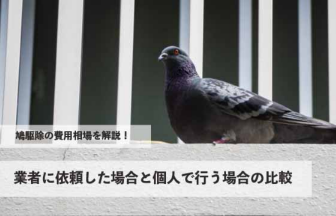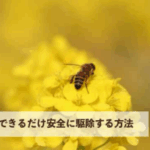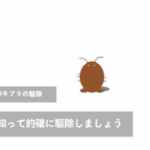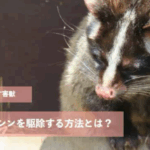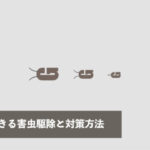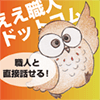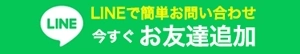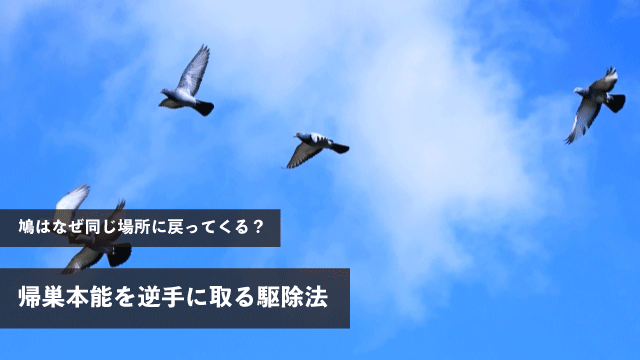
ベランダや屋根の軒先、太陽光パネルの下…。一度鳩に巣を作られた場所に、掃除しても何度も戻ってくる――そんなお悩みはありませんか?
実はそれ、鳩の「帰巣本能」による行動なのです。
本記事では、鳩の習性を深く理解し、それを逆手に取った効果的な駆除・予防方法をご紹介します。
鳩が同じ場所に戻ってくるのはなぜ?
ベランダを掃除したのに、また鳩が戻ってきた。
巣を撤去しても、気づけばフンが同じ場所に落ちている――そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
実はそれ、鳩特有の「帰巣本能」によるものです。
鳩の行動には一貫した習性と学習能力が関係しており、ただ追い払うだけでは根本的な解決にならないことも。
ここではまず、鳩がなぜ何度も同じ場所に戻ってくるのかという根本原因を詳しく解説していきます。
帰巣本能とは? 鳩が持つナビゲーション能力
鳩は古くから「伝書鳩」として使われてきたように、極めて優れた方向感覚と記憶力を持つ鳥類です。
これを支えているのが「帰巣本能」と呼ばれる本能的な行動原理です。
帰巣本能は「どんなに離れても巣に戻ろうとする力」
帰巣本能とは、鳩が自分の巣や縄張りの場所を記憶し、遠く離れた場所からでも再び戻ってこようとする習性のこと。
中には数百キロ離れた場所から数時間〜数日かけて帰ってくる個体もいるほどです。
この能力は以下のような要素に支えられているとされています。
- 太陽の位置や地磁気を利用したナビゲーション
- 目印となる地形や建物の記憶
- 嗅覚や音の記憶も関係している可能性
科学的にもその仕組みの一部は解明されていますが、まだまだ“神秘的”とされる部分も多く、鳥類の中でもとくに鳩の帰巣本能は群を抜いているといわれています。
一度「ここが巣だ」と学習すると、執着が強い
鳩は一度営巣に成功すると、そこを「自分の縄張り」と強く認識します。
そしてその場所が壊されたり掃除されたりしても、何度でも戻ってきて元の状態に復元しようとするのです。
この習性は繁殖行動とも深く結びついています。
鳩は年に数回繁殖し、そのたびに同じ場所で子育てを繰り返す傾向があります。
そのため、対策を怠ると毎年同じ場所で同じ被害を受けるリスクが高まるのです。
どんな場所が「快適」なのか?鳩が選ぶ理想の住まいとは
では、そもそも鳩はどんな場所に魅力を感じ、「ここに巣を作ろう」と判断するのでしょうか?
実は鳩が好む場所には明確な傾向があります。
鳩が安心して住める「4つの条件」
- 雨風をしのげる構造
- ベランダの屋根、庇(ひさし)、軒下、太陽光パネルの下など。
- 鳩は雨に濡れるのを嫌うため、屋根や壁に囲まれた場所を選ぶ傾向があります。
- 外敵が近づきにくい・死角が多い
- カラスや猫、人間がすぐに近寄れない空間。
- 特に集合住宅の高層階ベランダや、細い配管スペースは外敵から守られていると感じやすい。
- 静かで落ち着いた環境
- 鳩は神経質な面もあるため、人通りが少ない、音が少ない場所を好む傾向があります。
- 長期間留守にしがちな住宅や、使用頻度の少ないベランダは狙われやすい。
- 足場がしっかりしていて巣材を置けるスペース
- エアコンの室外機、窓枠の上、看板の上、太陽光パネルと屋根の隙間などは、巣材が転がりにくく安定する場所として好まれます。
一度快適と認識されると、何度でも戻ってくる
これらの条件が揃っていると、鳩は「ここは安全で快適」と判断し、次の繁殖期にも記憶を頼りに戻ってきます。
そしてまたフンをし、巣を作り、さらに鳴き声や羽音によって生活環境への悪影響が広がります。
重要なのは、掃除しただけでは“快適な場所”の記憶は消えないということ。
人間から見ればきれいになったように見えても、鳩の嗅覚や視覚、記憶の中には「巣のあった場所」という情報が残り続けています。
鳩の帰巣本能を“逆手に取る”とはどういうことか?
対策は「追い払う」より「戻らせない」こと
鳩の駆除と聞くと、追い払う・巣を壊す・フンを掃除する…といった対処法を思い浮かべがちですが、根本解決には至りません。
大切なのは「ここはもう住めない」「安全な場所ではない」と思わせることです。
つまり、帰巣本能を逆手に取り、「帰ってきても無意味だ」と認識させることが本質的な対策となります。
鳩を寄せつけないためにやるべき5つの対策

1. 物理的に侵入を防ぐ(防鳥ネットの設置)
防鳥ネットは最も確実な方法のひとつです。
- ベランダや太陽光パネルの下、エアコン室外機周辺をネットで物理的にふさぐ
- 鳩のサイズ(約30cm)を考慮し、網目は2cm以下が理想
- 張り方が甘いと逆効果なので、たるみや隙間がないように施工
この物理ブロックによって「戻ってきても入れない」と鳩に学習させることができます。
2. 忌避剤・超音波装置を併用する
防鳥ネットが設置しづらい場所には、忌避剤(臭いや味で鳩が嫌がる薬剤)や超音波装置の活用も効果的です。
- 忌避剤:ジェルタイプ、スプレータイプなど。定期的な塗布が必要
- 超音波装置:人間には聞こえない音で鳩を遠ざける
ただし、これらの効果は個体差があり、物理対策と併用することで効果が高まると考えましょう。
3. 鳩が嫌がる視覚的な仕掛けを使う
- フクロウの模型(天敵のフリ)
- CDや反射テープを吊るす
- 動く風車などの設置
これらの対策は視覚的な威嚇を目的としたもので、帰巣本能による「定着」を防ぐサポートになります。
4. フンや巣材を完全に除去・消毒
フンや巣材が残っていると、「ここは自分の縄張り」と認識されてしまいます。
- 手袋・マスク・保護眼鏡などを着用して清掃
- 乾燥したフンは粉塵化して吸い込むと感染症の原因にもなるため、事前に水を吹きかけてから拭き取り・回収
- 市販の消毒用アルコールや塩素系洗剤でしっかり殺菌
→清掃は単なる見た目の問題ではなく、再侵入防止に直結します。
5. 鳩が滞在できない「環境作り」
- 鳩の足場になりそうな出っ張りやスペースを減らす
- 室外機の上にトゲ状のスパイクやカバーを設置
- エサになるもの(食べ物・水)を置かない
「戻ってきても快適ではない」「住みにくい」と思わせることが最大の防御です。
放置するとどうなる?
- 鳩フンによる感染症(クリプトコッカス・オウム病など)
- 巣材に付着する鳥ダニの人間への被害
- 鳴き声や羽ばたきによる騒音・睡眠障害
- 酸性のフンによる建材の腐食や劣化
- 集合住宅の場合は管理組合とのトラブルや退去勧告
→一度被害が出ると、清掃・修繕費が高額になるケースもあります。
自分で対処できる?プロに頼むべき?

鳩の被害が発生したとき、まず悩むのが「これは自分で対処できるのか?それとも業者に頼むべきか?」という判断です。
結論から言うと、被害の程度や場所、鳩の状態によって大きく異なります。
「ベランダに少しフンが落ちているだけだから掃除すればいいかな?」と自己判断してしまうと、実は巣ができかけていたり、すでに卵を抱いていたりすることもあります。誤った処置は、法令違反や健康被害につながる恐れもあるため、しっかりと見極めが必要です。
DIYが可能なケース
以下のような条件に当てはまる場合は、ご自身で対策を講じることも可能です。
被害が軽度な場合
- フンが少し見られる程度
- 鳩がまだ常駐しておらず、飛来してくるのみ
このような状態であれば、フンの清掃や鳩よけネット・忌避剤の設置などで予防策を講じることができます。
高所作業を伴わない場所
- 低層階のベランダや軒先など、脚立や足場を必要としない範囲
安全性が確保されている場所であれば、ネットの設置や掃除も比較的安全に行えます。
作業に慣れている・衛生管理ができる
- フンの除去にマスク・手袋・消毒を徹底できる
- 鳩が嫌がる設置物のDIYや施工に慣れている
ただし、鳩のフンや羽毛にはクリプトコッカス症やオウム病などの感染症リスクがあるため、防護対策は必須です。
専門業者に依頼すべきケース
以下のような状況では、迷わず専門業者への依頼を検討すべきです。
すでに鳩が住み着いている
- 巣ができており、何度も鳩が出入りしている
- フンの量が多く、長期間放置されていた可能性がある
このような場合は、すでに縄張り認識されており、素人対応では再発リスクが高いです。撤去にも注意が必要となります。
高所作業が必要な場合
- ベランダの外側、ひさしの上、屋根裏、太陽光パネルの下など
足場の確保が難しい場所での作業は、落下事故の危険があるため非常に危険です。業者であれば安全対策や専用器具を用いて確実に作業できます。
鳩の巣に卵やヒナがいる場合
- 鳩の巣に卵が見つかった
- ヒナが生まれている状態
このケースは鳥獣保護管理法の対象になるため、個人が勝手に撤去することは法律違反となる可能性があります。特に注意が必要です。
【注意】鳩は「鳥獣保護法」の対象です

多くの方が見落としがちですが、鳩は「鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」の保護対象となっています。
この法律では、以下のような行為が原則として禁止されています。
- 鳩を捕まえる、傷つける、殺す
- 鳩の巣を壊す、卵を取り除く、ヒナを移動させる
たとえ自宅のベランダであっても、これらの行為を無許可で行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります(法第88条)。
空き巣でも油断は禁物
「もう鳩はいないようだし、巣を片付けても大丈夫かな」と自己判断してしまうケースは非常に危険です。
一見使われていないようでも、卵が巣材に隠れていたり、親鳥が不在の一時的なタイミングである可能性もあります。
違法行為とならないためにも、判断に迷う場合は必ず自治体や専門業者に相談しましょう。
業者であれば「鳥獣保護法に基づいた対応」が可能で、必要に応じて自治体への申請サポートもしてくれます。
まとめ
鳩の帰巣本能はとても強いもので、一度お住まいに巣を作ると、毎年同じ場所に戻ってくることがよくあります。
でも安心してください。この習性を理解して対策すれば、「ここに戻っても居心地が悪い」と鳩に認識させることで、再び巣作りされるのを防ぐことができるのです。
- 防鳥ネットで物理的に侵入を防ぐ
- 忌避剤や超音波装置で居心地の悪い環境を作る
- 巣材やフンをしっかり清掃・消毒する
- 鳩が止まれる場所をなくす工夫をする
このように複数の対策を組み合わせることで、鳩にとって「もう戻りたくない場所」という印象を与えることが大切です。
「どう対処すればいいか分からない…」という方は【一網打人】へお任せください。
- 鳥獣保護法に配慮した駆除に詳しい専門業者をご紹介
- 無料見積もりや初回調査サービスを提供する業者も多数
- 現代の住宅事情に合わせたベランダや太陽光パネルの対策にも対応
鳩被害は早めの対策が肝心です。放置すればするほど問題が大きくなってしまいます。
お困りの方は、ぜひ【一網打人】で信頼できる専門業者をお探しください。