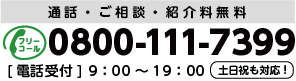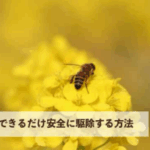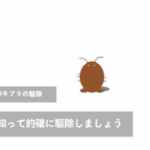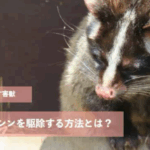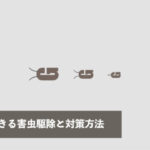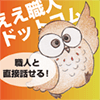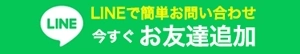「畑がハクビシンに荒らされた…」
「ハクビシンが屋根裏に侵入している…」
ハクビシンは畑の作物を荒らして回ったり、建物の屋根裏で暴れて騒音を出したりする害獣とされていて、ハクビシンによる被害にお困りの方は意外と多くいらっしゃいます。
そのため見つけたらぜひ駆除したいところですが、ハクビシンは「鳥獣保護法」によって保護されているためにむやみに捕獲したり殺傷するということができません。
そこでここではハクビシンの効果的な駆除の仕方について紹介していきたいと思います。
ハクビシンとはどのような生き物なのか

ハクビシンを効果的に駆除していくためにはまずハクビシンの生態を正しく理解することが重要です。
ここではまずハクビシンの生態について紹介していきます。
日本のハクビシンの生態について
ハクビシンはジャコウネコ科ハクビシン属に分類されている動物です。
日本では唯一のジャコウネコ科の哺乳類でもあり、基本的には外来種とされています。
野菜や果物を好むという性質があるために、みかん、ぶどう、かき、とうもろこしなどの畑を食い荒らす害獣となっています。
また、建物内に侵入すると屋根裏で移動する際にうるさい、糞尿被害がある、柱や家具をかじるといった被害をもたらします。
さらに病原菌を感染させるといった存在でもあるため、住み着かれると非常に迷惑な存在となっています。
ハクビシンの扱いについて
中国では古くからハクビシンを食べる習慣がありました。
肉に臭みがあるため、醤油などに付け込んで料理されることが多くなっています。
ただ、生息数が減少してきているために香港などでは野生動物保護法の保護対象となっています。
日本ではさまざまな損害をもたらすために「有害鳥獣」に指定されているのですが、同時に鳥獣保護法によって保護される対象でもあるため、むやみに捕獲や殺傷をすることはできません。
畑などに直接被害が出ている際には役所などに届け出をおこなったうえで駆除することが許可されていますが、ただ街中で見かけたからといって予防的に捕獲や駆除をすることは認められていません。
それがハクビシンの駆除をさらに難しくしていると言えるでしょう。
ハクビシンがもたらす被害とは

ハクビシンは人々の生活に多くの被害をもたらします。
そのため放置しているとどんどん被害は大きくなってしまうのです。
ここではハクビシンがいることでどういった被害がもたらされるのかについて紹介します。
畑や果物の木への被害について
ハクビシンは野菜や果物、特に糖度の高い果物を好んで食べます。
そのため畑が荒らされたり、みかんやぶどうなどの木が被害を受けることがあります。
また、ハクビシンは一度味を覚えるとその場所に何度も現れる習性があるために、被害を何度も受けることとなります。
糞尿被害について
ハクビシンが屋根裏などに生息すると大きな被害となるのが、この糞尿被害です。
ハクビシンは決まった同じ場所で排泄を行うという習性があるために、その場所に糞尿が蓄積されていくこととなります。
糞尿が溜まっていくことで蛆虫やゴキブリなどが発生したり、天井にシミをつくる、木材を腐食させていくといったことにつながってしまいます。
もちろん悪臭被害も起きてきます。
建物の衛生面を非常に悪化させることから人々の健康被害にも影響をもたらしていきます。
騒音被害について
ハクビシンが屋根裏に生息していると騒音被害が起きる可能性があります。
ハクビシンは夜行性ということもあり、屋根裏を走り回るのが夜中ということもあってより騒音被害を感じるのです。
また、5月前後に繁殖の時期があり、ハクビシンの子どもは泣き声が大きいためにこれも騒音となります。
建物の木材、断熱材などへの被害について
ハクビシンは建物の断熱材を引き裂いて自分の巣を作るのに利用するため、断熱材に被害が出ることがあります。
また、柱などをかじることもあるため、建物の断熱性や耐久性にも悪影響を及ぼすこととなります。
病気被害について
ハクビシンがもたらす病気としてはペットに感染する「猫ひっかき病」や「SARS」「ライム病」などがあります。
ハクビシンに直接触れたり、排泄物に触れなければ感染する危険性は低いのですが、長く放置しているとそれだけ感染の危険性は高くなることとなります。
ハクビシンを駆除する方法とは
ハクビシンは鳥獣保護法によって保護されているために、許可なく捕獲や殺傷をすることができません。
そこでここではハクビシンの被害を減らす方法、許可を得て駆除する方法について紹介していきます。
もっとも重要なのは「寄せ付けないこと」
ハクビシンは自由に捕獲できないために重要なのは「寄せ付けない」ということになります。
ハクビシンは特に果物を好むために、食べごろとなっている果実がそのまま木になっている状態はよくありません。
また、雑食でもあるため、生ごみなどが自由に荒らされる状態で放置されているのもよくありません。
しっかりと密閉できるごみ箱に捨てるということがポイントです。
その他にもペットの食べ残したエサ、ジュースなどの空き缶などもできるだけ清潔に管理しておきましょう。
近くに餌場が確保できなければ、巣を作るということも減ります。
「侵入させない」ことが重要
ハクビシンを屋根裏に住み着かせないようにするためには侵入経路を遮断してしまうのが効果的です。
侵入経路がなければハクビシンは建物内に住み着くことができません。
屋根裏まで登らせないために、「不要なものを置かない」「穴や隙間は塞いでおく」ということが重要です。
ハクビシンはわずかな隙間でも通ることができるので注意が必要です。
ハクビシンが嫌がる臭いを導線になりそうな経路に配置しておくことも重要です。
ハクビシンは「カプサイシンなどの刺激系」「石油系」の臭いを嫌がりますので、導線になりそうな場所にこうした臭いが出るもの、例えばトウガラシやニンニクのようなものを撒いておくのも効果的です。
ハクビシンを捕獲する場合は
ハクビシンを捕獲するためには自治体に捕獲許可申請をだす必要があります。
実際に建物に住み着いて被害が出ている、畑や果物の木が荒らされているという実害が出ている場合のみ許可がされます。
申請が許可されればハクビシンを捕獲するための「箱わな」「罠かご」を無料で貸し出ししてく
れます。
ハクビシンが通りそうな場所に設置しておき、罠にかかったら自分で処理をせずに役所に連絡をして罠ごとハクビシンを回収してもらうこととなります。
罠の設置方法などについても自治体で教えてもらうことができます。
ただ、罠を設置してもうまくかからない、正しく駆除できないという場合には専門の駆除業者に依頼するのが確実です。
ハクビシンや他の害獣を駆除してもらい、そういった被害に遭いにくいような環境を整える手伝いをしてくれます。
被害が大きい場合、続く場合などには利用するのがおすすめだと言えます。
まとめ

ハクビシンは、畑の作物や果樹を荒らすだけでなく、天井裏での騒音や悪臭、建物の破損、ノミやダニを媒介することで健康被害のリスクまで引き起こす、非常に厄介な害獣です。
しかし、ハクビシンは鳥獣保護法により保護されており、許可なく捕獲・殺処分を行うことはできません。
被害が発生した場合は、まず近寄らせない環境づくりが大切で、どうしても駆除が必要な場合は、役所へ捕獲許可の申請を行う必要があります。
多くの自治体では捕獲用の罠を無料で貸し出してくれるため、それを活用するのも一つの手段です。
とはいえ、捕獲申請や許可の手続き、適切な捕獲方法や再侵入防止策など、個人では対応が難しい場面も多くあります。
特にハクビシンのような警戒心の強い動物を安全かつ確実に駆除するには、専門知識と経験が不可欠です。
そんなときは、害虫・害獣駆除の専門業者を紹介するポータルサイト「一網打尽」の活用をおすすめします。
一網打尽では、信頼できる業者だけを厳選して掲載しており、地域や被害の種類に応じて最適な駆除業者を見つけることができます。
ご自身で悩む前に、ぜひ一度、一網打尽をご覧ください。
被害の再発防止までしっかりサポートする専門家が、あなたの不安を解消します。