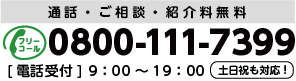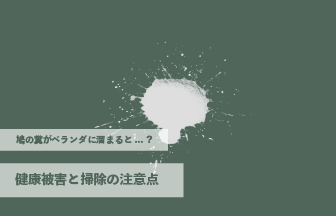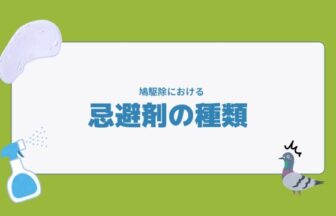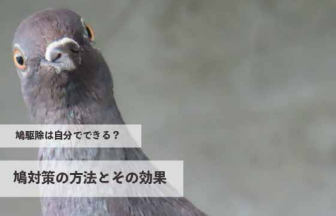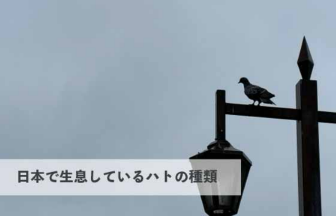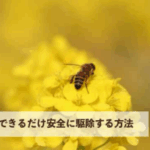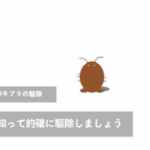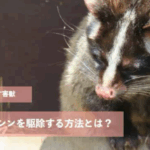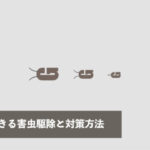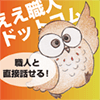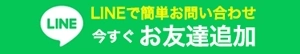都市部に住んでいる方の中には、「最近ベランダの手すりが汚れている」「天井裏からバサバサと羽音が聞こえる」といった経験をされたことがあるかもしれません。それ、もしかしたら“ハト被害”かもしれません。
ハトは都市の環境に適応した身近な野鳥である一方、フンによる汚染や巣作りによる騒音など、住環境に大きな影響を及ぼす害鳥でもあるのです。とくに近年では、住宅密集地や高層マンションの増加に伴い、被害報告が全国的に増加傾向にあります。
この記事では、「ハト被害が多い地域はどこなのか?」という疑問に答えながら、それぞれの地域特有の傾向や、効果的な対策方法までをわかりやすく解説していきます。
目次
被害が多いのはどんな地域?「都市部×集合住宅」が狙われやすい理由

人が多く、エサが豊富な都市部はハトにとって楽園
ハト被害が集中しているのは、東京・大阪・名古屋・福岡といった大都市圏です。これらのエリアは人口密度が高く、駅前や商業ビル、飲食店の数も非常に多いため、食べ残しや生ごみといった“エサ”が常に豊富な状態です。
また、都市部では外敵も少なく、電柱やビルのひさし、マンションのベランダなどが安全な「巣作り場所」として利用されやすいため、ハトにとって非常に居心地が良いのです。
高層マンションやビルのひさしが「格好の営巣地」に
近年とくに深刻化しているのが、タワーマンションや高層ビルにおけるハトの営巣です。ハトは高所を好む習性があり、10階以上のベランダでも平気で飛来し、巣を作ることがあります。
このような高層住宅では、「まさかこんな高さまで来るとは思わなかった」と、対策が遅れるケースも少なくありません。さらに、人の出入りが少ない共有廊下や外階段の上部なども、ハトにとっては安全な場所と認識されやすいのです。
【地域別】ハト被害が多い都市の傾向と具体例

ハトの被害は全国で見られますが、特に顕著なのは「都市部」「観光地」「古い住宅密集地」など、ハトにとって“住みやすく”“食べ物が豊富”な場所です。ここでは、実際に被害が多く報告されている主要都市について見ていきましょう。
【東京都】高密度エリアと公園周辺に要注意
東京都内では、新宿区・中野区・足立区・杉並区などを中心に、ハトのフン害や営巣の相談が多く寄せられています。特に新宿や渋谷などの繁華街に近いエリアでは、飲食店のゴミ出しが多く、ハトが群れを成して集まる傾向が見られます。
また、代々木公園・上野公園・井の頭公園などの大きな公園周辺では、来園者が餌を与えることでハトが定着し、近隣の住宅やマンションに被害が波及する例も少なくありません。
「ベランダの手すりにいつもフンがついている」「子どもの遊ぶスペースに鳩が常駐している」など、子育て世帯や高齢者のいる世帯からの相談が特に多いエリアです。
【大阪市】古い建物が多い地域で被害が顕著に
大阪市では、天王寺区・生野区・西成区・中央区といったエリアで、ハト被害の報告が増えています。これらの地域は、築年数の古い集合住宅や店舗併用住宅が密集しており、隙間からハトが入り込みやすい環境が整ってしまっているのです。
また、大阪城公園や天王寺動物園周辺など、観光・文化施設に人が集まりやすいスポットは、餌付けや食べこぼしによってハトが集中する傾向にあります。
「シャッター上部や室外機の裏に巣を作られた」「管理組合が対処しても戻ってくる」といった相談が多く、再発性の高さが特徴です。
【名古屋市】ビル街・駅周辺マンションでの営巣が問題に
名古屋市でも、中区・中村区・昭和区といった中心部で、ハト被害が深刻化しています。特に名古屋駅や栄駅周辺の高層マンション・雑居ビルでは、ベランダやひさし部分にハトが営巣し、フン害・騒音・羽毛の飛散といった被害が多数報告されています。
また、地下鉄の換気口や空調設備など、人目につきにくい場所に巣を作るケースも多く、管理会社側が気づく頃には大量のフンが堆積していることも珍しくありません。
特に共用部の対処には管理組合の合意が必要となるため、「すぐに対応できない」というストレスも住民の間で大きな問題になりがちです。
【福岡市】公園周辺・繁華街での被害が目立つ
福岡市では、中央区(天神・赤坂)や博多区(博多駅周辺)でのハト被害が頻繁に見られます。とくに大濠公園や舞鶴公園といった自然環境の整ったエリアは、ハトの繁殖に適した環境であり、近隣のマンションや飲食店でフンや巣によるトラブルが多発しています。
さらに、天神地区ではビル屋上や外壁の窪み、庇(ひさし)の上などがハトの定着ポイントになっており、高層ビルでも安心できない状況です。
「エントランス上部に毎年巣を作られて困っている」「店舗の看板の上が糞で汚れてしまう」といった声が多く、清掃費や営業妨害の被害も深刻なのです。
なぜハトが集まりやすい地域とそうでない地域があるのか

「なぜこの地域ばかりハトの被害が多いのだろう?」という疑問を抱いたことはありませんか?
実は、ハトが好んで集まる場所にはいくつかの共通点があるのです。
ハトは「餌・安全・居心地」で集まる
ハトは、野生の鳥とはいえ、人間の生活圏に強く依存している動物です。とくに以下の3つの条件がそろうと、その地域に定着しやすくなります。
餌が豊富にあること
コンビニや飲食店が多く、食べ残しやゴミ出しが頻繁な地域では、ハトが簡単に食料を得ることができます。
さらに、公園や広場で人から直接餌を与えられる機会が多いことも、被害を増やす大きな要因です。
外敵が少ないこと
自然の中ではハトはカラスや猛禽類の餌食になることもありますが、都市部ではそうした外敵が少なく、安心して暮らせる環境が整っています。
加えて、屋上や庇の陰など、人目につきにくく外敵に襲われにくい場所が豊富であることも、安全性の面で大きな魅力となります。
繁殖しやすい環境があること
ハトは、わずかな隙間や平坦な足場があれば、営巣(巣作り)を始めてしまいます。
古い建物のひさし、室外機の上、看板裏、ベランダの片隅などは、巣を作るのにちょうどいいスペースなのです。
このように、「餌があり、安全で、居心地がいい」場所には、ハトが何度でも戻ってきてしまうのです。
人間の行動がハトの定着を後押ししている
本来、ハトは臆病な性質を持っています。ところが、都市部では人に慣れた個体が多く、人間の生活リズムに溶け込んでいるのが実情です。
たとえば、
- 公園でのエサやり
- マンションのベランダでの放置ゴミ
- 飲食店周辺の食べ残し
- ゴミの分別不足や回収の遅れ
こうした人のちょっとした行動が、結果的にハトにとって快適な環境を作り出してしまっているのです。
さらに、ハトの帰巣本能(一度住み着いた場所に何度でも戻ってくる習性)により、追い払ってもすぐに戻ってくることがよくあります。
「このあたりでなら安全に子育てできそうだ」と判断されてしまうと、巣を壊しても新たな場所に再営巣する可能性が高くなってしまいます。
居住環境ごとのハト対策ポイント

ハトの被害対策は、住んでいる建物の構造や管理体制によって変わってきます。自分の住まいに合った対応をとることで、無駄なトラブルや被害の拡大を防げるのです。
戸建て住宅では「侵入防止」と「こまめな掃除」がカギ
戸建て住宅の場合、ハトの被害はベランダや屋根の上、ひさし、換気口の周辺などに集中しやすい傾向があります。
とくに、屋根の隙間や2階のベランダ、エアコンの室外機の上などは、ハトにとっては格好の休憩所や巣作り場所になってしまうのです。
戸建てでの対策として重要なのは、物理的な侵入防止と環境の清潔維持です。
たとえば、
- ネットやトゲ状の剣山(バードスパイク)を設置する
- 巣作りされやすいスペースに物を置かない
- フンや餌の残りなどをすぐに掃除しておく
こうした「寄せつけない環境づくり」が何よりも大切なのです。
また、敷地内でのエサやり行為を家族や近隣の方にやめてもらうよう、丁寧に協力を求めることも効果的です。
賃貸マンションでは「まず管理会社へ報告」
賃貸マンションでは、自分の部屋のベランダなど「専有部分」だけでなく、「共用部」にもハトが現れるケースが多く見られます。
とくに以下のような場所は要注意です。
- 非常階段や外廊下
- 屋上、駐輪場、ゴミ置き場
- エントランス上部や照明の陰
このような場所で被害が出ている場合、入居者が勝手に対策を講じることは避けるべきです。
まずは必ず管理会社や大家さんへ状況を報告し、対応方針を相談するのが原則です。
また、ハト避けネットなどの設置を希望する場合も、管理規約や使用細則に沿って許可を得る必要があるため、自己判断は禁物です。
写真付きで状況を説明すれば、管理会社側も対応しやすくなります。
その後、建物全体の管理体制で、共用部を含めた適切な対策がとられることが望ましいのです。
分譲マンションでは「管理組合と協力してルール作りを」
分譲マンションでは、個々の居住者の責任だけでなく、管理組合としての意思決定が不可欠となります。
ハトの被害が共有部分に及んでいる場合、管理組合での協議を経て、建物全体としての対策を講じる必要があるのです。
たとえば、
- 「ハトへのエサやり禁止」を明文化した掲示を出す
- 巣ができやすい屋上や看板裏に物理的な対策を導入する
- 専門業者による定期的な調査や駆除を予算化する
こうした対応は、居住者同士の合意形成を前提に行う必要があります。
個人の努力だけでは限界があるため、管理組合に働きかける姿勢が何よりも重要となってくるでしょう。
また、被害が深刻な場合は、理事会にて「鳩対策専門業者の導入」や「共有部清掃の強化」などを正式に議題化することも検討してください。
専門業者に依頼するメリットとは?

自力での対策には限界がある
ベランダにネットを張ったり、忌避剤を設置したりと、自分でできるハト対策はある程度限られています。とくに高所や構造の複雑な場所、共用部に及ぶ被害などは、住人だけで完全に解決するのは難しいのが実情です。
また、ハトの被害が進行すると、フンによる悪臭や健康被害、建物の劣化といった深刻な問題につながるおそれもあります。こうした状況を根本的に改善するには、やはり専門業者の力が必要なのです。
専門業者ならではの強みとは?
ハト対策の専門業者は、単なる駆除だけではなく、被害の原因や建物の構造に応じた「再発防止策」までトータルで提案してくれるのが大きな特徴です。
具体的には、以下のような対応が可能です。
- 現地調査による侵入経路や被害範囲の特定
- 建物ごとの構造に適したネット・剣山などの設置
- 忌避剤や超音波機器の併用による多層的な対策
- 法律(鳥獣保護法)に準拠した巣の撤去や処分
- アフターフォローや定期メンテナンスの実施
とくにマンションなどの集合住宅では、共用部の施工にも対応できるかどうかが重要になります。その点、実績豊富な専門業者であれば、管理会社や理事会との調整も含めてスムーズに対応してくれるでしょう。
コストはかかっても「長期的な安心」が得られる
専門業者に依頼するとなると、やはり費用面を気にされる方も多いかと思います。ただ、何度もハトが戻ってきたり、フン被害が再発したりすることを考えると、長期的にはコストパフォーマンスの良い選択といえるのです。
さらに、業者によっては初回調査無料・保証付きプランなどを用意しているところもあるため、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。
「駆除」と「予防」は別物?その違いと必要性

被害が出てからの「駆除」では遅いことも
ハト対策というと、「まず駆除しなければ」と思いがちですが、実は駆除と予防ではアプローチがまったく異なるのです。
駆除とは、すでに巣を作られてしまったり、フン被害が広がったりと、すでに発生した被害に対処する行為です。一方で予防は、「ハトが寄りつかない環境をつくる」ことに主眼を置いた取り組みです。
この違いを理解していないと、「一度駆除したのにまた戻ってきた」といった繰り返しのトラブルに悩まされることにもなりかねません。
再発を防ぐには「多層的な予防」が不可欠
ハトには非常に強い帰巣本能があります。いったん巣を作った場所には何度でも戻ってくる性質があるため、単なる一時的な追い払いでは不十分です。
そのため、駆除と並行して以下のような予防策を講じることが重要になります。
- 侵入経路を塞ぐ(ネット設置など)
- 滞留しやすい場所をなくす(室外機の上など)
- 忌避剤や超音波装置で接近を防ぐ
- フンの清掃と消臭で「縄張りサイン」を消す
このような多重的な対策を「総合防除(そうごうぼうじょ)」と呼ぶこともあります。
予防と駆除は「片方だけ」ではなく、「両輪」として考える必要があるというわけです。
まとめ
マンションでの鳩被害は、放置してしまうと深刻化しやすく、住環境の衛生面だけでなく、住民間のトラブルや建物の劣化にもつながってしまうおそれがあります。
とくに共用部での被害や対策は、個人の判断だけでは解決が難しいケースが多いため、管理組合や管理会社と連携しながら計画的に対策を進めることが重要です。
本記事では、マンション管理組合が行える鳩対策の基本と、注意点、具体的な対策方法について解説してきました。
- 被害が出る前の「予防」が鍵
- 共用部の工事は事前相談が原則
- 鳥獣保護法に配慮した対応が必要
- 専門業者の力を借りることで再発防止が可能
こうしたポイントを押さえて、安心できる住まいを維持していきましょう。
もし現在、すでに鳩被害でお困りの場合は、早めに管理会社や駆除業者に相談してみてください。
全国の鳩・害鳥対策に対応した業者が見つかる【一網打人】では、被害状況に応じた適切な専門業者の紹介が可能です。
まずはお住まいの地域で信頼できる対策業者を探してみてください。
よくある質問(Q&A)
Q. ベランダに勝手に鳩よけネットを張ってもいい?
A. 多くのマンションでは、外観の統一や避難経路の確保の観点から、ベランダへの設置物に関するルールが定められています。そのため、勝手にネットを張ることはトラブルの原因になりかねません。
管理規約や使用細則には「設置時は管理組合の許可を要する」といった記載がある場合も多く、事前に確認して許可を得てから設置するのが原則です。
Q. 鳩の巣を見つけたらどうしたらいい?
A. 鳩は「鳥獣保護管理法」により、無許可での巣の撤去や捕獲が原則禁止されています。たとえベランダに作られた巣であっても、勝手に処分してしまうと違法となるおそれがあるのです。
そのため、まずは管理会社や専門業者に相談するのが適切な対応といえるでしょう。状況によっては自治体に許可申請を行った上で、合法的に対応を進める必要があります。
Q. 対策しても鳩が戻ってくるのですが?
A. 鳩には非常に強い帰巣本能があります。過去に巣を作った場所や、安心して休めた場所には、何度も戻ってくる習性があるのです。
そのため、ネットや剣山など物理的な侵入防止策だけでなく、忌避剤や視覚的な威嚇具を組み合わせた「多層的な対策」が必要不可欠です。
また、清掃・消臭を徹底することも重要です。フンには縄張りのサインとなるフェロモンが含まれており、それが残っていると再び寄り付いてしまうリスクが高くなります。