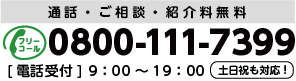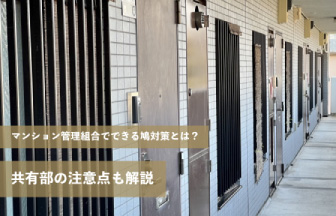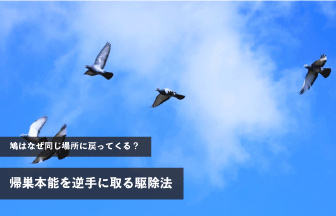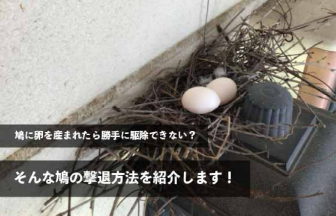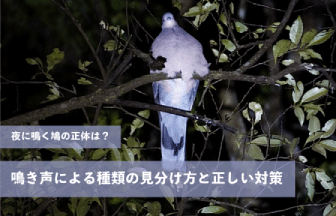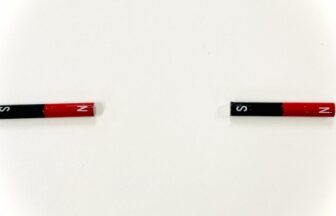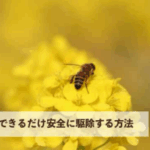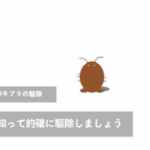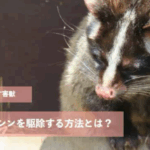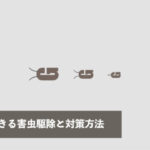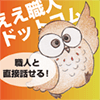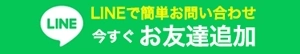普段生活している街中でもよく見かけるハトですが、それらの中にも種類があり、比較的よく見かけるものから天然記念物に指定されているような珍しい種類のものまであります。
平和の象徴とも言われ、国民にも馴染みの深い鳥ですが、大量に発生すると害を及ぼす鳥であることには違いありません。
そこでここではそんな日本で見かけることができる7種類のハトについて紹介していきたいと思います。
目次
ドバト(カワラバト)について

ドバトは正式名称は「カワラバト」と呼ばれるハトで、おそらくもっともポピュラーなハトでもあります。
「ハト」と言われればまず連想されるのがこのハトと言えます。
もともとはヨーロッパ、中央アジア、北アフリカなどが原産であり、日本の在来種ではありません。
しかし古くから日本に生息しており、北海道から沖縄まで幅広く分布しています。
「食用」「伝令用(伝書バト)」「愛玩用」など人間とのかかわり方もさまざまです。
ただ、「人になつきやすい」「群れて行動する」といった特徴によって、大量に発生することで大きな被害をもたらすことも多くあります。
群れで行動する際の鳴き声や糞など多くの被害が出てしまうのです。
キジバトについて

古くは「ヤマバト」と呼ばれており、その名前の通りに山岳地帯、山林、森などに生息していたために人間とそれほど関わることはありませんでした。
しかし山林開発などが進み、人間の生活範囲が広がることで少しずつ人間の生活圏に近づいてきました。
今ではドバトと同様に街中で見かけることもあるハトです。
全体的には茶色っぽい色をしていますが、灰色の羽がキジに似ていることからキジバトと呼ばれるようになりました。
問題は「ホーホー」「デーデーポッポー」と鳴く雄の求愛行動の際の鳴き声です。
これが早朝にさえずりされるため、騒音被害につながっています。
カラスバトについて

カラスバトは比較的カワラバトに近い種類のハトです。
ただ、カワラバトよりは少し体が大きく、カラスのように黒っぽい羽をしています。
その体は光の当たり方によって紫色、緑色に光り輝いて見えるために美しいハトとして扱われています。
日本では本州の中部より南の常緑広葉樹林に生息していることが多く、海岸付近や離島などで見かけることがあります。
カラスバトはその個体数が少なく、環境庁は「準絶滅危惧(NT)」に指定しています。
亜種である「アカガシラカラスバト」は国の天然記念物に指定されており、国内希少野生動物種となっています。
そうした特徴があるハトのために、人間の生活圏に大量に生息することはなく、ほとんど見かけることもないハトだと言えます。
キンバトについて

キンバトは街中で見かけることはほとんどないハトです。
日本では宮古島以南の南西諸島にのみ生息していて、大きさはそれほど大きくはありません。
南西諸島の鳥らしく、光沢のある美しい緑色の羽、赤いクチバシが特徴的です。
頭頂部の色がオスとメスで違っており、頭頂部が青色、灰色がかっているのがオス、褐色なのがメスです。
その美しさからバードウォッチングの対象となったり、野鳥カメラマンが撮影したりする人気の鳥となっています。
植物食傾向が強く、果実や種子などを好んで食べます。
薄暗い森林の地面を歩きながらエサを探すことが多くなっています。
とにかく珍しい鳥でもあり、森林に住み着いている上に警戒心が強いことからなかなか見ることはできません。
また、国の天然記念物に指定されている鳥でもあります。
アオバトについて

アオバトも昔はキジバトのように「ヤマバト」と呼ばれることがありました。
日本、中国、台湾だけで生息している絶対数の少ない鳩でもあり、繁殖数も少ないとされています。
羽がオリーブ色、エメラルドグリーンということもあり、数の少なさからも野鳥好きから貴重とされている鳩となっています。
絶対数が少ないために巣を発見するのも難しく、「ウーオーウー」と唸るような声で鳴くというのも特徴的です。
また、「海水を飲む」「まれに数百話単位で飛来する」といった謎の行動をとるのも神秘的です。
ベニバトについて

中国を含めた東アジアで多く分布している鳩ではありますが、基本的には大陸に生息している鳩であり、日本には渡り鳥として西日本に飛来してくることがある程度です。
そのため、大陸では珍しい鳩ではありませんが、日本で見るのは珍しい存在となっています。
鳩の種類の中でももっとも小さい鳩となっており、大きいものでも25cm程度しかありません。
植物食傾向が強く、地面の草の芽や種子などを好んで食べます。
オスの羽はレンガのような赤褐色をしていて首付近に真っ黒の模様があります。
メスは全体的に灰褐色をしていて、脚が暗褐色です。
シラコバトについて

シラコバトは日本では関東地方の北東部で生息しています。
千葉県北部、埼玉県東部、茨城県西部などがその中心でもあり、埼玉県越谷市で市の鳥に、埼玉県で県の鳥に指定されています。
以前は狩猟対象となっていたためにその数が激減しており、1956年には国の天然記念物に指定されました。
一時期数が増えてきていたのですが、鳥インフルエンザなどの際に再び数を減らしています、
全身が灰褐色をしていて首の付近に黒い模様があります。
日本で騒音や糞害をもたらしているには主に2種類のハトである

日本では鳩が群れをなして生息することで騒音や糞害などをもたらすことがあります。
ただ、すべての鳩がそれに当てはまるわけではなく、街中で生息しているのは主に「ドバト」と「キジバト」の2種類であることがわかります。
ということはこの2種類の特徴がわかっていれば被害への対策もしやすいということになります。
ここでの特にこの2種類の鳩の特徴を紹介します。
ドバトについて
ドバトとキジバトの2種類の中でも特に注意しなければならないのがこのドバトです。
ドバトは「群れを作って集団行動する」という特徴があるため、数十羽単位で騒音や糞害をもたらすのがこのドバトだからです。
ドバトは集団でエサの場所や天敵の情報、巣を作る相談などをしているとされています。
そのため、「忌避剤を設置する」「ネットで侵入を防ぐ」「電流を流して退治する」という対策をしていくことで、「この場所には近寄らない方が良い」という情報を広めることが可能となります。
ドバトが集団で住み着き始めたら、できるだけ早く対応することが重要だと言えます。
キジバトについて
キジバトはドバトとは違って群れで行動することはあまりありません。
「単独」もしくは「つがい」で行動することが多くなっています。
また、ドバトよりも警戒心が強く、人間が近づくとすぐに逃げていくためにあまり人間に関わろうとしません。
それに対してドバトは人間が近づいても「エサがもらえる」と判断して近づいてくることさえあります。
もともとキジバトは山林で住むという性質もある通り、それほど人間に害を加える鳩ではないのです。
まとめ
日本で見かける鳩は主に7種類いることがわかりました。
その中でも街中で見かけることがあるのは主に「ドバト」と「キジバト」の2種類となっており、騒音や糞害などの被害をもたらしてくるのは「ドバト」であると言えます。
ドバトは集団を作って行動するだけでなく、人間にも警戒心が薄いために人間の生活圏と関りが深くなっているのです。
そのため、鳩による被害の対策をする際には主にドバトへの対策をすることとなるでしょう。